
分からないところは、厚生労働省の担当課さまへ電話して確認しました。
お忙しい中、ご丁寧に回答いただきありがとうございました!
令和3年6月3日『改正育児・介護休業法』が国会で成立しました。
今回は、『育休を取る予定の男性』及び『夫にも育休を取って欲しいと思っている女性』目線で、記載していきます。
何も分からない方のため、知識ゼロから学べるように体型立てて記載しています。
早速、ご質問から。
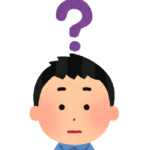
今回の法律改正、いつから始まるの?
結論、段階的に始まります。
今回の成立をもって、主な内容は来年の令和4年4月1日から施行(開始)されます。
そして、一部は公布日(2021年6月9日)から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行。(つまり、令和4年12月頃までには施行)
義務付けというちょっと厳し目の内容に関することは、令和5年4月1日から施行されます。

主に、男性が育児休業を取りやすくするための法律改正です。
今回の改正で『男性版産休』を創設したと言われていますね。
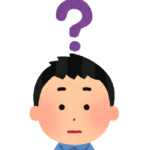
育休じゃなくて産休?
産休は女性だけの休みでは?
今回は、『法改正のポイント』『男性の育休の内容』『今回企業に課せられた義務化』についてまとめていきます。
なお、お金(給付金)関係の話は大きく変更になっていないので、あくまでも休業に特化して記載します。
まだ、育児休暇を取得したことがない初心者の方でも分かるように”グラフやフローチャート”を使って、解説していきますね。
結論、男性は、“出生後1年間”でMAX「計4回に分けて」育児休業を取れます。
飛ばし読みをすると、過去の制度とゴチャゴチャになり理解が難しくなるのでご注意ください。
それでは、早速一緒にみていきましょうっ!
○ 仕事と育児、を両立できる支援制度についてゼロから学びたい
○ 今回の『改正育児・介護休業法』の概要及び内容を、詳しく知りたい
○ これから、育児休業を取得予定の会社員や公務員
○ 妻のために、育児休業を検討している“男性”会社員や公務員
授乳以外、男性でも【子育てに関する全ての事】に参加できる

まずは、育児休業の実態を知っておくことから始めましょう。
こちらは、【内閣府 男女共同参画局】の育児休業取得率のデータを用いて、作成したグラフになります。
令和元年の最新のデータでは、日本人の男性の育休取得率はたったの16.4%です。
近年右肩上がりとは言え、10人中2人以下の男性しか育児休業を取得しないなんて、ちょっと考えさせられます。
ちなみに、このグラフを使って過去記事で、他人から騙されずに、正しく情報を読み解く方法について解説しましたね。

子育てに主体的に関わろうとする男性が増えれば、女性の負担が偏っている現状を変えることができます。
そうなんです。先
ほどのグラフは『男性の育休取得率が低い』という驚きの数字と共に、『女性に子育ての負担が偏っている』という事実を表しています。
「今回の新しい制度を活かすかどうか?」
それは、これから育休取得予定の男性はもちろん、超少子高齢社会の日本で若い人からの税金で支えられていく全ての中高年や高齢者にとっても、重要な問いかけになります。
ハッキリ言いましょう。これからの日本に赤ちゃんが生まれないと、年金の制度設計の見直しに拍車がかかるからです。
厚生労働省が本日、令和3年6月4日発表した2020年の人口動態統計によると、合計特殊出生率は1.34人でした。5年連続の低下となり事態は深刻です。

【授乳以外の子育てに関する全ての事】に参加資格のある、男性の覚悟が問われています。
これまでの【仕事と育児の支援制度】を理解しよう

厚生労働省 / MHLWchannel 知っておきたい 育児・介護休業法 より引用
こちらの画像は、出産から記載がありますが、女性が取得できる産前から確認していきましょう!
原則6週間の【産前休暇】(女性のみ可能)
産前休暇と産後休暇を合わせて【産休】と言います。
まずは、【産前休暇】です。
これは労働基準法で定められており、「出産予定日の6週間前から(双子以上の場合は14週間前から)」本人が職場へ請求すれば産前休暇を取得できます。出産日は産前休業に含まれます。

なお、公務員の場合は「出産予定日の8週間前から」と、民間企業より2週間早く取得できます。
公務員は恵まれていると思うかもしれませんが、それは半分正解です。(後述します)
女性の方は妊娠が分かったら、出産予定日や休業の予定を職場(上司)へ申し出ましょう。これが、“妊娠の報告”となります。

「出産後も仕事を続けたい!」という希望をはっきりと伝えましょう。
妊娠出産を理由に労働者を解雇・パートへの契約変更をすることは、『男女雇用機会均等法』に抵触する違法行為です。
なお会社側は、妊婦健康診査を受診するために下記の回数を確保しなければなりません。
- 妊娠23週までは4週間に1回
- 妊娠24週から35週までは2週間に1回
- 妊娠36週以後出産までは1週間に1回
- 医師等がこれと異なる指示をした場合はその回数
これは、『男女雇用機会均等法施行規則第2条の3』で決められています。
上記により勤務しなかった日(時間)の給与の取り扱い「有給か?無休か?」は、会社の定めによります。

公務員の場合は、実施していない地方公共団体もありますが「妊婦健診休暇」は有給扱いですね。
また、上記の妊婦健康診査で主治医から働き方について「休憩が必要」「入院が必要」など指導を受けた場合は、指導内容を会社に申し出てください。

医師からの指導事項を、正しく会社に伝えるためにも「母性健康管理指導事項連絡カード」に記載してもらうと効果的です。

厚生労働省 母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について より引用
会社側はこれにより、『妊娠中の休憩に関する措置・通勤緩和・妊娠中の症状に対応する措置』を講じなければなりません。
会社に規定がなくても、契約社員・アルバイトなどの方でも、産前・産後休業及び、下記を申し出ることが可能です。必ず、本人から申し出てください、そうすれば会社側に拒否権はありません。
- 危険有害業務(重量物・有毒物質)の就業制限(労働基準法第64条の3)
- 軽易業務への転換(労働基準法第65条)
- 時間外・休日・深夜業の制限(労働基準法第66条)

休み中に、出産予定日が1週間延びてしまった…。
産前休業期間の6週間を超えて休んだ分はどうなるの?
回答します。
予定日よりも遅れて出産した場合は、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。
なお、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は「産後休業」として確保されます。
産前休暇を取得する時点の出産予定日を少し早めにすると、民間の場合でも「公務員と同じ8週間」近く休めますね。
原則8週間の【産後休業】(女性・改正により実質男性も可能)
出産の翌日から8週間は就業することができません。そもそも働ける身体ではありません。
ただし、産後6週間を経過後に本人が会社へ請求し、医師が認めた場合は就業することができます。
ちなみに会社側は、産前・産後休業期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。

そして、今回の改正で男性も産後休暇のような『男性版産休』が創設されました。
男性版産休の改正は以下のとおりです。【重要です】
- 子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(これが通称、男性版産休)
- 子の出生後8週間以内に4週間まで、休業を取得することができる
- 上記は2回に分割して4週間まで取得できる(例:出生時から2週間+里帰りから戻るタイミングで2週間)
- もちろん、1回で4週間続けての休業でもOK
幸せな家庭を築き上げるためにも、これらを活用しない手はありません。
ぜひ活用して奥さんの、産後うつ(マタニティーブルー)を阻止しましょうっ!
次は、育児休業についてです。
以降、『パパ休暇』という制度を既にご存知の方は、記憶から消してください。(事実上、この制度を網羅する形の法改正となったため。)

これとゴチャゴチャになり、厚生労働省へ電話しました。
原則1年間の【育児休業】(女性も男性も可能)

今回の改正で、休業の申出(必ず書面にて)期限については、原則休業の2週間前までと期日が緩和されました。
現行の育児休業(1ヶ月前)よりも短縮されたのです。これは嬉しい^^!
なお、子が1歳に達するまで、本人の申出により育児休業の取得が可能です。(変更なし)
平成29年10月1日からは、保育所に入れないなどの場合は、最長で2歳まで延長が可能になっています。

公務員の場合は、2年目以降は無給になりますが、3年間育児休業可能です。
これは、公務員の恵まれた福利厚生としか言いようがありません。
最長で2歳まで延長する際の、注意点は延長の申し出の期日です。
子どもが1歳になった後に保育所に入れないなどの場合は、追加で半年間休業を始める2週間前までに申し出ることが必要です。
また、子どもが1歳になるまでの間に期間を延長することもできます。その場合は、当初終了しようとしていた日の1ヶ月前までに申し出が必要です。

そして、今回の改正で大きく変わったことがあります。
『労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。』
忙しい年度末などだけ、スポットで労働してもらう仕組みも取り入れられました。
これは、雇用主にメリットがありますね。
私たちは「えっーーー!」って感想です。
会社からお声がかかった時は、家の労働を極限まで無くす方法をするしかありません。
給料関係とか複雑になりそうですね。いったいどうなるのか…。

そしてそして、今回の改正でもう1つ大きく変わったことがあります。
育児休業及び介護休業の取得要件で「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」が休みを取れる、という要件を廃止しました。

出典:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
つまり、まだ働いて非正規雇用で1年経っていなくても原則休業できます。
ただし、「労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。」とあります。
自分がまだ働いて1年未満の非正規雇用の方は、雇用契約書などを確認しましょうね。
ここまでの内容を【フローチャート】で確認しよう

厚生労働省 男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集 より引用一部編集
このフローチャート重要です!
このフローチャートの理解でOKです。もう一度言いますが、パパ休暇は無くなったと考えてください。
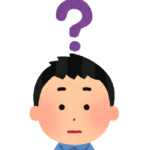
あれ?「子の出生後8週間以内に2回に分割して4週間まで休める」ってのは、ここまで読んで理解したけど。
よく見ると、子の出生後8週間以降も2回休んでるのなんで?
回答は、「それも、今回の改正された内容だから」です。

- 【男性版産休】…子の出生後8週間以内に2回に分割して4週間まで休める。
- 【(普通の)育児休暇】…育児休業(男性版産休を除く。)についても、分割して2回まで取得することを可能に改正。
『男性版育休+育児休業の分割取得』が可能になったのです。厚生労働省グッジョブ!

通常の場合は、ここまでの理解で100点満点です。
ここからは、保育所に入れないなどの場合は、最長で2歳まで延長が可能となった場合です。
そのフローチャートが、隠れていた部分です。

結論、2回延長(半年更新)して最長2年にした場合、男性は計6回に分けて育休を取得できます。
また、開始時点が1歳または1歳6ヶ月時点に限定されていた要件が、開始時点を柔軟化することにより、途中交代で育休が可能になりました。
まぁ、「へぇ…ふぅん…」くらいの認識で良いと思います。
なぜなら万が一、保育園に入れなかった場合は役所へ行き、その場合のケースについて個別相談すれば良いからです。

現時点の法律の情報だけでは、なかなか理解できないよ。
お国さま、将来的に分かりやすいパンフレットお願いします!
【まとめ】+義務化について

- 育児休業の申出期限については、これまでの1ヶ月前までから、原則休業の2週間前までと期日が緩和された。
- 男性は、子の出生後8週間以内に、2回に分割して4週間まで休めるようになった。【男性版産休】
- 男性版産休を除き、通常の育児休業も分割して2回まで取得することが可能になった。
- 上記により、男性は、出生後1年間でMAX「計4回に分けて」育児休業が可能になった。
- 育児休業中でも忙しい年度末などだけ、スポット労働できるようになった。
- 育児休業及び介護休業の取得要件で「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」が休みを取れる、という要件が廃止された。

ーーーここからは初めての情報ーーー
- 妊娠・出産の申出をした個別の労働者に対して、制度周知・休業の取得意向の確認をするよう、雇用主に義務化された。
- 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主(大企業)に対し、育児休業の取得の状況について公表することが義務化された。(これだけは、令和5年4月1日から)

出典:Yahoo!ニュースオリジナル「男性の産休」新設が決定
主な内容は以上になります!

ね。結論だけ読んでもよく理解できないでしょ?
最初から読まないと、なかなか難しかったと思います。
長文な記事、たいへんお疲れ様でした。
なお、会社や企業側、上司や管理職目線での記事も、「企業側が知らないとやってしまう“違法行為”」について記載しており、とても参考になりますのでご覧ください。
今回、難しくてよく理解できなかった方も、育休取得者目線の記事も読めば、育休についてマスターできますよ。
実際に、これから育休を取るようになる男性は、今後増えてくると思います。
そんな時に、その同僚や上司、他の社員から嫌がらせの行為をされたり、制度利用を邪魔されたりする「パタニティハラスメント(パタハラ)」があると最悪です。
「パタニティ(paternity)」は、父性という意味です。
国民一人ひとりが、日本の超少子高齢社会に目を向けて、男性が育休を取りやすい法整備・職場環境がもっともっと良くなり、社会全体に明るく新しい産声が広まっていけば良いなぁと思いました。
今回は、お金(給付金)関係の話はしませんでしたが、基本的に若いうちから資産形成をしてFIREを目指している状態であれば、会社員であれ公務員であれ、お金の不安は少なくできます。
最後にもう一度。授乳以外、男性でも【子育てに関する全ての事】に参加できます!

問おう。私は育児休暇を取りますが、“あなたはどうしますか?”
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
まだまだ、始まったばかりのブログですが、リピート訪問は私たちの励みになります。皆さまの【お気に入りブログ】となれるよう、これからも魂込めて更新いたします。記事への感想・コメントだけでも大変心強く、更新の励みになり嬉しいです!どうぞよろしくお願いいたします。








コメント