『仕事を上手に断ること』が苦手な公務員の方はいませんでしょうか?
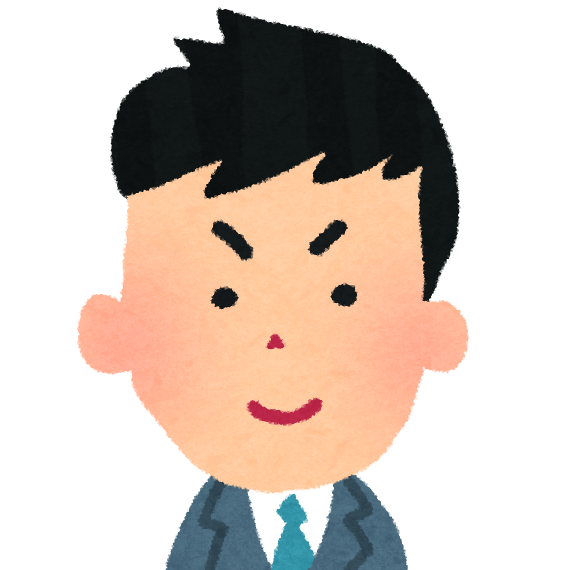
公務員の仕事は今や、“何でも屋”になりつつあります。
事務分掌以外にも、
- 「あの人の仕事を手伝っている」
- 「席が新人の隣なので、実質新人のサポートをしている」
- 「災害が起きたからそっちを優先しないといけない」
- 「自分のいる係に仕事が降ってきたので、その手伝いをしないといけない」
など、例を挙げるとキリがありません。
これら全てを受け入れようとすると、仕事が溜まってしまい自分の業務が終わらなくなります。
すると、仕方なく残業をして、残業をしても結局終わらずに悩んでしまい結果的に、周りにも迷惑をかけてしまうという『負のループ』に陥ってしまいます。
仕事が【終わらない・多すぎる・難しい・できない】の対処法は、以前記事にしましたので、現在進行形で困っている方はまずはこちらからお読みください。
今回は【仕事を断る】具体的方法に内容をフォーカスして、お伝えしていきます。
やりたくないことや、できないことを無理して引き受けた経験が皆さんにもあると思います。

今回の内容は、かなり即効性のある内容なので、覚えたその日からバンバン日常に取り入れていきましょうっ!
- 『断る = 拒絶』と勘違いしている方
- 「断ると、相手に不愉快な思いをさせてしまうのでは…」と思い込んでいる方
- 残業を多くしている方
- 仕事を断ることに苦手意識のある方
まずは【断るための言葉】を身につけよう
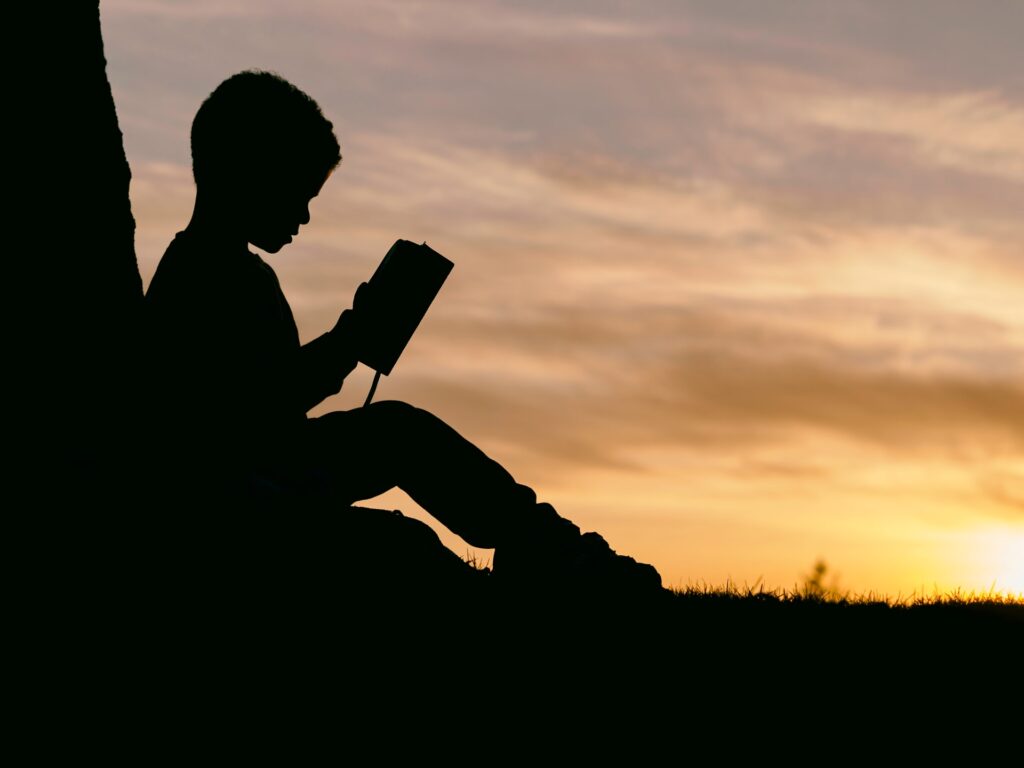
普段から無意識に使っている言葉が、あなたの印象を作っています。
特に“相手にとって”印象に残る場面は、『自分がお願い仕事が断られてしまった時』です。
なので【仕事を断る】という言動には、注意しなければなりません。

「マイナスの口調」が習慣化している人は、良い人間関係を築くことが難しいです。
したがって、内容は断っているのに「プラスの口調」を使って、周囲との関係を良いものにしつつ、結果自分の仕事を軽量化する言葉を伝授します。
「今は厳しいですが、夕方頃であれば可能です」
何かを頼まれた時に、忙しさを理由に断るのはよくあることです。
この時のポイントは、いつまでならできるのかを明示することです。
すると、内容は「今は忙しいから無理」と言いつつも、代案を提案しており、自分の現状をキチンと説明しているのです。

この言い方であれば相手は、嫌な思いはしていないですね。
応用的には、
- 「今週は厳しいですが、来週でしたら可能です」
- 「今部長からの資料作成を頼まれているので、それが終わり次第であれば可能です」
- 「午後の会議資料を作っているので、それが終わり次第なら」
など結構使えます!
自分の現状を伝えること・できない理由を添えること・代案を相手に与えること、この3つが重要です。
すると、断られた方も「そういうことか」と理解して不愉快な思いはしませんし、あわよくば別の人に仕事をお願いするかもしれません。

「今ちょっと忙しいので無理です」なんて言った日には、“あの人は忙しさを理由に断る人”という、レッテルを貼られてしまいますよ。
「私にはまだそのスキルがないので難しいです」
これは、できない理由を正直に相手に伝えることに特化して、仕事を断る方法です。
「業務内容の引き継ぎをしていません」「〇〇という言葉、初めて聞いたのですが、私にできるか正直不安です」など、正直ベースの言葉です。
すると、相手は『できない部分をフォローする』『その人ができない部分だけ別の人に頼む』など、完全丸投げではなく何かしらの対応や手段を考えなくてはなりません。

これを言って、仮に仕事を貰っちゃったとしても、相手はフォローしてくれたり丁寧に教えてくれたりなど、自分自身のスキルアップにつながりますね。
「私には無理です!」では、スキルアップも何もありません。
相手を不愉快にして、かつ自分自身の成長する機会も逃してしまいます。
「別の方法でもいいですか?」
「部長との会議時間を、電話で調整しておいて」と頼まれたとします。
その時あなたは、部長へ提出すべき資料を持っていたとすると、その時に会った時に“ついでに”相手の仕事を終わらせることが可能ですよね。
なので、電話ではなく直接会うという方法を取りたいので、上記タイトルの言葉を使うのです。

相手が余程、結果よりプロセス(過程)を大事にする人以外は、あなたのリクエストは承認されることでしょう。
頼まれた時に、頭の中で『より簡単に・より早く・より快適に』頼まれごとを処理をする、ということを考えることは重要です。
代案を出すことにより、お互いが歩み寄り、折り合いをつける方向で話し合えば自然と着地点が見えてくることが多いのです。
よって、代案ベースの言葉により相手から頼まれた仕事をそのままするのではなく、違ったアプローチをしてみることでその仕事を処理しましょう。きっと解決できる問題が減りますよ。

相手がこちらからの代案を受け入れてくれたら、感謝の言葉を伝えましょうね。
嫌われる勇気!大切です。
【誤解を招く言葉】は使わないで仕事を回避しよう

日本語はなかなか難しいもので、誤解を招く言葉というものがあります。
【誤解を招く → 仕事で間違える → 仕事のフォローが必要になる → 仕事が増える】といったような状態が続きます。
したがって、そもそもの普段の会話の中で誤解を招く言葉は使わない方が無難です。

下記のような言葉は、便利でつい使ってしまいますね。
「大丈夫です」
「あっ、大丈夫です」「大丈夫でした〜」など、プライベートではすごく便利な言葉なんだけど、仕事上で使うと痛い目に遭うのがまずこの言葉ですね。
『大丈夫』という言葉はもともとは、「しかっりしていて安心できる様子」を表す言葉です。
したがって、「分かりました」「できます」の意味で使われるのが一般的でした。
しかし、最近では反対の意味の「やりません」「いりません」といったような、断り文句として使われることが多くなりましたね。

これ、よかったらどうぞ〜
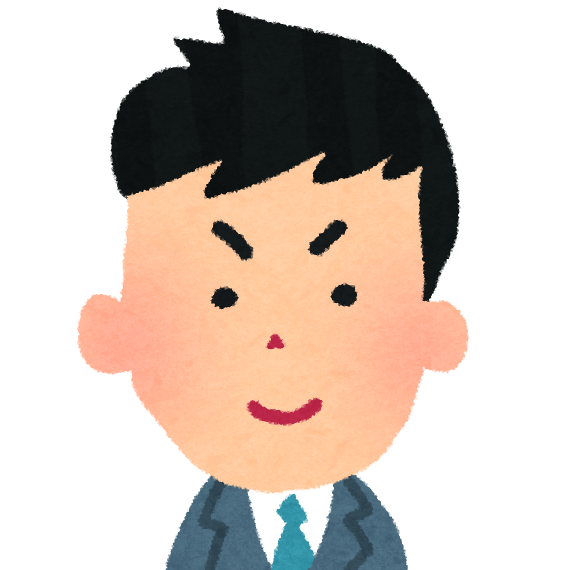
あ、大丈夫でーす…。
といった具合に使われます。若い人ほど使っているのではないでしょうか。
プライベートではこの「大丈夫です」で、すれ違いが起きることは少ないです。
いったいなぜでしょうか?
それは、親しい人と話す場合は、お互いの話グセを知っているのですれ違いが起きにくいからです。

しかし、仕事上ではあまり多様しない方が良いでしょう。
ビジネスシーンでは、「YES」とも「NO」とも取れる言葉を使うのは、問題の原因になりかねません。
できるときは「できます」「分かりました」、できないときは「できません」「厳しいです」などハッキリと意思を伝えましょう。
「この仕事挑戦してみるか!?」→「大丈夫です…」で仕事を引き受けないようにしましょう。
「結構です」
悪徳の電話で「〇〇の不動産物件の購入どうですか?」と聞かれ、「結構です!」と答えたとすると、相手の悪徳不動産はその声を録音し、購入のための準備に取り掛かることでしょう。
こちらも、誤解を招く言葉ですね。
不要なときは「不要です」「いらないです」、必要なときは「必要です」「欲しいです」とキチンと意思を伝えましょう。

その他は、「大丈夫です」の内容と同じことです。
これ以上の説明は「大丈夫です」ね?
「なるほど」
これも、つい使ってしまう言葉ですね。
相槌代わりに「なるほど、なるほど」「なるほどですね〜」みたいな感じです。
しかしこれ、相手にとっては結構不愉快に感じる言葉なんです。
なぜなら、上の空で他人事のように相槌されているように感じるからです。
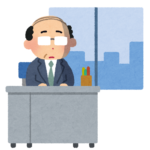
「あ〜、なるほどなるほど。なるほどねぇ…」
「あなたちゃんと聞いてますか?」とツッコミたくなりますね。
別に、なるほどを使ってはいけない訳ではありません。
キチンと「何を」理解したのかを伝えれば問題ないんです。
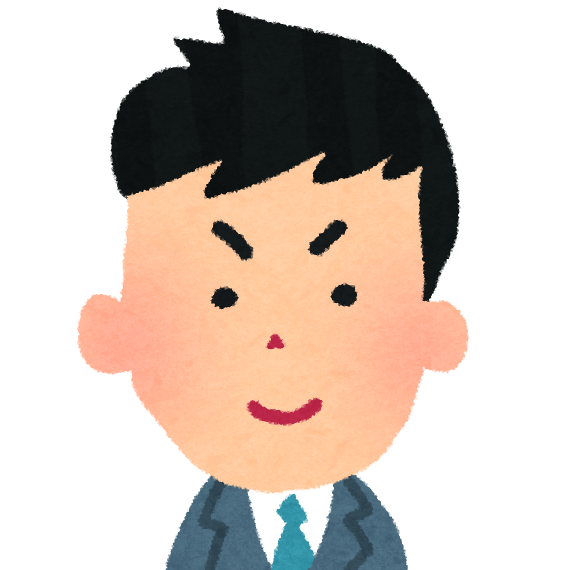
なるほど。明日までに〇〇をすれば良いのですね!
こう回答してもらえれば、キチンと仕事を引き受けてくれたのだなと、相手は感じることでしょう。
「なるほど」+「お断り」でもOKです。
「なるほど。しかし、これから営業回りに行くのでちょっと引き受けられません」といった方が、「これから営業回りに行くの引き受けられません」とストレートにいうより相手は傷つきません。
なぜなら、最初の「なるほど」で相手のことを共感しているからです。
「なるほど」「そうなんですね」「伝わりました」などにプラスして、相手に伝えたい本心をセットで使うと、相手を傷つけることなく仕事を回避できるかもしれません。
いつもの言葉に気をつけよう

「芸は身を助ける」という言葉があります。
『習い覚えた技(芸)にすぐれていれば、困った時に生活を助けてくれたり、暮らしの役に立ったりする』という意味です。
今回記載した内容は、全て即効性があります。
まずは、日常生活中でバンバン使っていきましょう。それから、ビジネスシーンにそれらの言葉を落とし込むのです。

私たちは、日本語を自由に操れると思っています。
しかし、実際は決まり切ったいくつかのフレーズを繰り返し使っています。
したがって、習慣となっている口癖はいつも、不意に口からこぼれます。
それが、相手を追い詰め、自分にブーメランで返ってくるとすると目も当てられない結果になるでしょう。
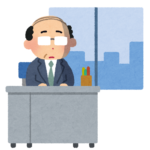
「君は今日も残業するのかね?」

いつもはそうですね。しかし今日は水曜日です。
したがって、今日は早く帰って妻へ料理を振る舞おうと考えています。
では、ノー残業デーなのでお先失礼します!
ノー残業デー(水曜日)にはスパッと帰る。これを仕事の断る理由に使ってもOKです。
「自分の気持ち」を抑え込み、相手を優先すると、我慢する・耐えるということが増えます。
時には自分ファーストで考えて、仕事を断る時があっても良いのです。
ですから、自分のためにも自ら発する言葉に注意を向けて欲しい。
そのためには、自分も相手も大切に、使う言葉を考えて豊かな人間関係構築していきましょう!
こちらの本は、言葉を言いかえることに特化した本で例文などもあり参考になりました。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
まだまだ、始まったばかりのブログですが、リピート訪問は私たちの励みになります。皆さまの【お気に入りブログ】となれるよう、これからも魂込めて更新いたします。記事への感想・コメントだけでも大変心強く、更新の励みになり嬉しいです!どうぞよろしくお願いいたします。






コメント